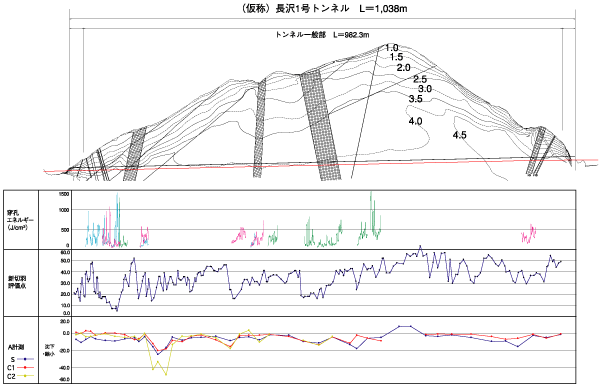山岳トンネルにおける新しい技術の導入
長沢1号トンネル
山陰支店 工事事務所
小山 起男
はじめに
本工事は、島根県益田市内における国道488号の付替道路バイパスのトンネル新設工事です(図-1)。当社が開発した以下の新しい技術を本トンネル工事で導入・実証しましたので、その効果について紹介します。
- 温度制御噴霧式覆工コンクリート湿潤養生工法
- トンネル地山評価システム
|
図-1 位置図 |
温度制御噴霧式覆工コンクリート湿潤養生工法
1.技術導入の背景
山陽新幹線でのトンネルにおける覆工コンクリートはく落事故以降、覆工コンクリートの高品質化、高耐久性化が求められています。そこで、これまで標準では実施されなかった覆工コンクリートの養生の重要性が見直され、各種養生方法が提案されています。
2.技術の概要
本工法は、覆工コンクリート打設用の全断面スライドセントルの後方に、31.5m長(セントル3スパン・養生7日間分)の移動式の養生台車を連結させ、この台車に霧噴霧ノズルや閉塞用シートを搭載して、覆工コンクリートの養生を行うものです(写真-1)。
養生台車には、遮水シートおよび端部締切用の空気充填膜(風船)が取り付けてあり、覆工コンクリート表面と遮水シート間に30~60cmの密閉された空間が確保できます。この空間に微粒の霧を噴霧することで湿度約100%の養生状態に維持できます。また、温度感知センサーと噴霧水の温度制御システムにより、初期材齢時のコンクリートにとって最適な温度での養生が可能となります。なお、養生台車はセントルに装備された走行モーターで容易に牽引可能な構造としています。
3.効果検証試験結果
現場導入後、噴霧養生あり区間となし区間を設け、養生空間の温湿度測定、覆工コンクリート内部温度測定、テストピース強度試験、シュミットハンマー強度試験等を実施して比較検証を行いました。一例として、図-2にテストピース圧縮強度試験結果を示します。「噴霧養生」を実施した供試体は、強度発現が早くかつ噴霧養生(7日間)を終えた以降も順調に強度増加し、材齢91日では35.8N/mm2と「標準養生」(20℃恒温水槽内養生)の供試体と同程度で、養生をしない一般的な坑内「気中養生」に比較して20~50%も強度増加がみられました。試験結果より、脱枠から材齢7日間の噴霧養生を実施することがコンクリートの強度発現に対して有効であること、材齢初期の乾燥収縮ひび割れ発生の低減効果があること、耐久性の向上に有効であることが実証されました(ET439号参照)。

|
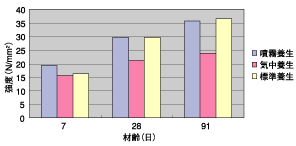
|
トンネル地山評価システム
1.システムの概要
本システムは、油圧ドリルジャンボによる地山穿孔時の機械データ(穿孔速度、打撃圧力、回転圧力等)から切羽前方地山状況を予測する技術(前方探査技術)を中心に、切羽観察評価点、坑内変位計測データを関連づけて一元管理するシステムです。
2.前方探査結果
本現場で実施した切羽観察評価点と前方探査の結果を図-3~5に整理しました。穿孔エネルギーとは、穿孔速度と打撃圧力に基づき算出した地山の硬軟を定量的に把握するための指標数値です。
これらの結果から、本現場では、穿孔エネルギーが200J/cm3、切羽評価点が20点という閾値(いきち)を、掘削補助工法が必要となる目安とすることができました。また、これらの結果は、岩判定の際に、地山状況にあった鋼製支保工サイズ、吹付けコンクリート厚、ロックボルト長・本数等のトンネル支保パターンを決定する上で重要な判断資料となりました(ET421号参照)。
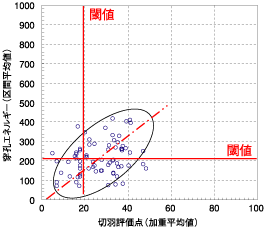
|
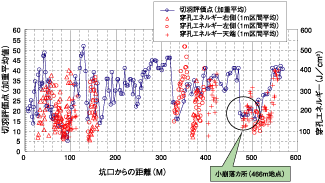
|
|
図-5 トンネル地山評価システムによる出力例(一部編集) |
おわりに
平成20年4月現在、トンネル施工はL=1,014mの掘削とL=844mの覆工コンクリートの施工を完了しています。
今後も新しい技術の適用により、トンネル構造物の高品質・高耐力化に貢献できるものと考えています。本トンネルの施工事例が、今後の山岳トンネル工事の参考になれば幸いです。
| 工事名称 |
一般国道488号長沢バイパス改築(改良) (仮称)長沢1号トンネル工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 島根県益田市長沢町地内 |
| 発注 | 島根県 |
| 施工 | 鴻池組・大畑建設・原工務所特別共同企業体 |
| 工期 | 平成18年3月~平成20年12月 |
| 工事内容 |
工事区間延長 L=1,048m トンネル延長 L=1,038m (掘削断面積 54.8m2 仕上断面積 47.4m2) 坑門工 2カ所 コンクリート舗装 8,181m2 |
本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。