日本初のGRV連続ウェール方式を用いた型枠支保工
皿垣連続高架橋上部工
九州支店 工事事務所 工藤茂彦
/ 亀山 博通
はじめに
有明海沿岸道路は、福岡県の南西部で地域高規格道路として建設が進められており、福岡県大牟田市~ 佐賀県鹿島市に至る延長55kmの路線で、三池港、佐賀空港等の広域交通拠点と大牟田市、柳川市、大川市、鹿島市などの有明海沿岸都市郡を連携し、地域間の交流促進と国道208号の交通安全確保を目的としています。
本工事は、皿垣連続高架橋上部工のRC18径間連続開腹アーチ橋を施工しており、当工事で使用したGRV連続ウェールシステムを紹介します。
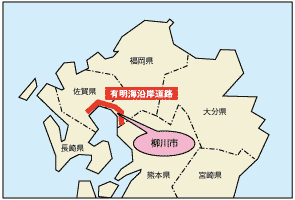
|

|
GRV連続ウェール方式を用いたアーチリブ型枠支保工の概要
このアーチ橋の特徴は6種類の曲率を持ち、18径間の連続するアーチ部(合計42基)により、上部の床版を支える構造です。1つのスパンごとに1列から4列へとアーチが配列され、また、3スパンごとにアーチの形状が変わっていく構造のため、アーチ部の線形変化に対応し、転用も容易なPeri社(ドイツ)の GRV連続ウェールシステムを日本で初めて採用しました。
システムの特徴
- 多様な曲線形状への適合
- 型枠・支保工組立・解体の省力化と安全性の向上
- 3分割ユニット構造による移動性・転用効率の向上
組立概要
1. センターパネル
- GRVウェーラー部材を連結ピンにより接続し、STSボルトにより調整、固定します。
- ヘビーデューティースピンドルでトラス構造に組み立て、スチールウェールと結合してGRVウェールを支えます。
- 支保工部は、センターパネルを四角塔式支保工(STシステム)にて支えます。
2. サイドパネル
- 各部材を連結した後、ヘビーデューティースピンドルにてGRVウェールを支えます。

|

|

|
|
GRV連続ウェール方式施工手順
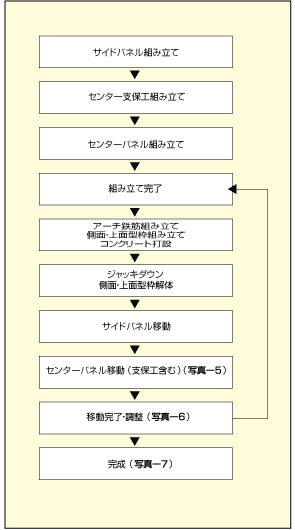
|



|
|
図-3 完成パース図(出典:国土交通省パンフレット) |
おわりに
従来の工法では、H形鋼をアーチ形状に沿って曲げ加工し、大引材として使用する等が考えられますが、連続アーチ橋の場合は転用性・施工性、解体時の安全性 において検討が必要となります。今回このGRV連続ウェール方式を用いることにより、異なるアーチ形状にも容易に対応でき、少人数で効率的に施工を行って います。 今後、類似工事において参考になれば幸いです。
| 工事名称 | 福岡208号 皿垣連続高架橋上部工工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 福岡県柳川市大和町中島地内 |
| 発注 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 施工 | (株)鴻池組 |
| 工期 | 平成18年5月~平成20年2月 |
| 工事内容 |
橋梁形式:RC18径間連続開腹ア~チ橋 工事延長423m 幅員:上り線10.15m 下り線9.65m RCア~チ部製作工42基 鉛直材100基 床版工11基 壁高欄1,060m 鋼製排水溝694m |
本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。
