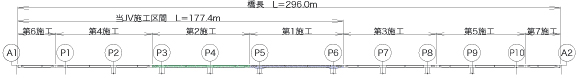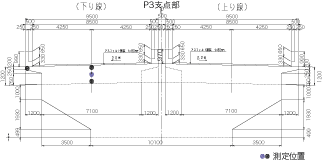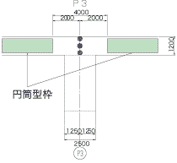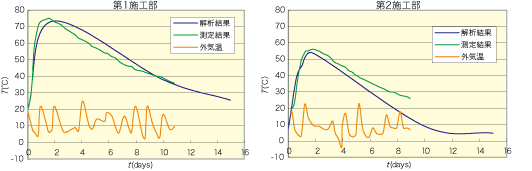中空床版ラーメン橋の温度ひび割れ対策
国道408号真岡北バイパス
東京本店 工事事務所
小山 富紀
はじめに
本工事は、栃木県真岡市(もおか)における全長296.0mのPC11径間連続中空床版ラーメン橋(うち6径間L=177.4mが当JV施工区間)の上部工建設工事です。
主桁の大部分の断面は中空形状ですが、橋脚直上部は中実断面であり、断面寸法を考慮するとマスコンクリートとして取り扱う必要があります。
そこで、事前にコンクリートの温度応力解析を行い、対策工を検討しました。検討の結果、部材の中心部と表面部の温度差によるひび割れ(内部拘束ひび割れ) が予想されることから、対策として部材内外の温度差の低減を主とした入念な養生を行いました。養生にあたっては、コンクリート打設開始から養生期間中のコ ンクリート温度を測定し、解析結果と比較しながら実際のコンクリートの温度状態をモニタリングしました。
本号では、本工事のうち第1・第2施工部(図-1)主桁コンクリート橋脚直上部の温度測定結果と解析結果の比較および施工時に行った養生方法について紹介します。
|
図-1 施工個所位置図 |
コンクリート温度の解析結果および測定結果の比較
(1)施工条件
第1・第2施工部主桁コンクリートの施工条件を表-1に示します
(2)温度測定位置
第1・第2施工部ともに、解析結果によってひび割れの発生が懸念された橋脚直上部の主桁断面内で、図-2、3に示す4個所(第1施工部はP6支点部上り線、第2施工部はP3支点部下り線)のコンクリート温度を測定しました。コンクリート温度の測定には写真-1に示す熱電対記録計を使用しました。
(3)温度測定結果
代表個所として、最高温度を示す個所である橋脚直上部の主桁断面中心(図-2、3中、青丸印)のコンクリート温度について報告します。
第1・第2施工部それぞれについて、材齢とコンクリート温度の関係を解析結果と測定結果を併せて図-4に示します。これらの関係をみると、最高温度と最高温度到達時の材齢も、解析結果と測定結果が近い値を示していることが分かります。第2施工部において、最高温度到達以降の温度降下が解析値より測定値の方が緩やかなのは、保温養生の影響と考えられます。
|
表-1 施工条件
|
|
図-2 測定位置断面図 |
図-3 測定位置側面図 |
|
写真-1 熱電対記録計 |
|
図-4 解析結果と測定結果の比較 |
施工時養生方法
主桁コンクリートは解析結果により、ひび割れの発生が懸念されたため、入念な養生を実施しました。特に第2施工部は寒中施工となり、慎重な施工が要求されたため、下記に示す方法で養生を行いました。
- 外部足場側面を風よけおよび保温を目的にブルーシートにより囲みました(写真-2)。(下面は全面足場板敷き)
- 打設日前日からジェットヒーターを使用し、型枠および鉄筋を凍結しないよう暖めました(写真-3)。
- 打設後は被膜養生剤を散布し、表乾を防止しました。
- 表面硬化後、養生マットを敷設し温水による湿潤養生を行いました。
- 養生水の凍結防止のため、養生マット上面にはブルーシートを敷設しました(写真-4)。
- 日中は発熱した熱を放散させるため、ブルーシートを剥がしジェットヒーター稼働台数を減らすなどして、周辺温度の調整に努めました。
1~6の方法により、ひび割れの発生原因である部材内外の温度差の低減に努めるとともに、表面の乾燥を防止し、寒中コンクリートとしての凍結を防止しました。

写真-2 足場側面シート養生 |

写真-3 ジェットヒーター運転状況 |

写真-4 表面保温用ブルーシート |
おわりに
温度解析と実施工におけるコンクリート温度測定によって、コンクリートの状態を的確に把握することができました。
この事例がコンクリート構造物のひび割れ防止の一助となれば幸いです。
| 工事名称 | 国道408号真岡北バイパス江川橋(仮称)上部工建設工事その1 |
|---|---|
| 工事場所 | 栃木県真岡市下籠谷 |
| 発注 | 栃木県 |
| 施工 | 鴻池・若築特定建設工事共同企業体 |
| 工期 | 平成17年3月~平成19年3月 |
| 工事内容 |
施工延長…177.40m 最大支間…40.00m 有効幅員…8.50m 全幅員…19.50m |
本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。